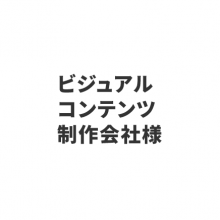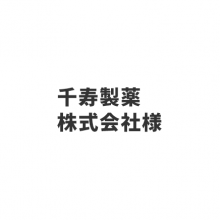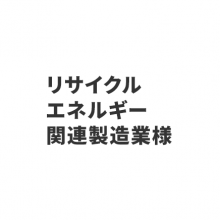インタビュー参加者
◆ガイオ・テクノロジー様
取締役副社長 岩井 陽二様(写真中央)
ソリューション事業本部 技術3部 安田 荘太様(左から2番目)
サービス&ツール事業本部 技術4部 技術41グループ 小林 竜馬様(左から1番目)
◆ウェッブアイ
サービス本部 サービスグループ PMO2チーム
サービス本部 社員A(右から2番目)
社員B(右から1番目)
目次
- はじめに
- PMO導入のきっかけとウェッブアイを選んだ決め手
- 現場が語るPMOとの協業
- オンライン環境下での工夫と岩井様への報告
- プロジェクトの「健全性」とPMO導入による変化
- 現場で実感するPMOの価値と「攻めのPMO」像
- PMOに求められる資質と今後の展望
はじめに
ー本日はお集まりいただきありがとうございます。まず初めに、ガイオ・テクノロジー副社長である岩井様にお伺いします。ガイオ・テクノロジー様の事業概要と、お客様へ提供されているサービスや製品についてお聞かせいただけますでしょうか。
岩井様:我々は創業から45年ほど経つ会社です。もともとは、組み込みシステム向けのクロスコンパイラを開発する会社としてスタートしました。1980年代に合併を経て現在のガイオ・テクノロジーという社名になりましたが、一貫してツールを開発し販売する「ツールビジネス」を手掛けています。もう一つの柱が、2008年のリーマンショックを機に立ち上げた「エンジニアリング支援」のビジネスです。それ以前は、合併先が手掛けていたハードウェアとファームウェアの受託開発事業を行っていました。現在は、このツールビジネスとエンジニアリング支援の二本柱で事業を展開しています。

ーありがとうございます。そのツールビジネスとエンジニアリングサービスは、どのようなお客様に提供されることが多いのでしょうか。
岩井様:特に特定の業界に絞っているわけではありませんが、現在の売上の約95%は自動車業界のお客様です。もともとは製造業全般、いわゆる「組み込み」と呼ばれる領域の企業を相手に事業を展開してきましたが、現在では自動車業界が中心となっています。お客様である自動車業界の企業が組み込みソフトウェアを開発される際に、我々のツールやエンジニアリング支援を提供している、という形です。
PMO導入のきっかけとウェッブアイを選んだ決め手
ーそうしたビジネスを展開される中で、ウェッブアイのPMOをご採用いただきました。ご採用のきっかけは何だったのでしょうか。
岩井様:きっかけは、とあるプロジェクトマネジメントツールを導入したことでした。しかしツールを使ってプロジェクト管理をしようと試みたのですが、どうもうまくいかなかったのです。そこで、これはツールだけではダメで、プロジェクトを専門にサポートするスタッフが必要なのではないかと思い立ちました。そこでプロジェクト管理ツールの開発・提供・活用支援やコンサルティング等を手がける御社であればPMOサービスも適切にして頂けるのではないかと思い、御社にご連絡させていただいたのが始まりです。
ープロジェクト管理ツールの導入だけではうまくいかない、という課題があったのですね。具体的に、どの部署からPMOの導入を始められたのでしょうか。
岩井様:特定の組織に限定したわけではありませんが、最初にPMOを導入したのはエンジニアリング支援の部隊でした。この部隊は、お客様の要求をヒアリングし、エンジニアリング支援のための技術提案を行い、それを実行してお客様に成果物(価値)を提供するという一連の流れを担っています。しかし、そのプロセス全体を第三者に分かりやすく説明するためのプロジェクトマネジメントや、価値を伝えるための資料作成などが、うまく回っているプロジェクトばかりではなかったというのが事実です。そこでPMOを活用し、プロジェクトを健全な(ヘルシーな)状態にしたいと考えたのが、導入の直接的なきっかけです。
ー数あるPMOサービス提供会社の中から、弊社ウェッブアイを選んでいただいた決め手は何だったのでしょうか。
岩井様:実は、以前に他社へも声をかけたのですが、満足のいく提案が得られませんでした。そんな折、御社はもともと「工程's」というプロジェクト管理ツールの検討をした際にお付き合いがあったので、きっとPMOサービスもあるだろうと考えたのです。

ー弊社の森川が年賀メールを差し上げた際に、思い出していただいたと記憶しております。その後、北関東の支社で動いていたプロジェクトで、弊社から2名のPMOスタッフが現場常駐という形でトライアル支援に入らせていただきました。その時の経験から、ウェッブアイに任せられそうだと思っていただけたのでしょうか。
岩井様:そうですね。当時の担当者からは「ウェッブアイのPMOはかなり積極的に”グイグイ”働きかけてくれるから良い」と聞きました。エンジニアはシャイで、面倒くさがりな側面があります。彼らに任せきりにすると、プロジェクトを健全に運営するために必要な業務が、なおざりになってしまうことがあるのです。そこをPMOが積極的に関与して、プロジェクトが円滑に進むように働きかけてくれることを期待していました。その期待に、ウェッブアイのPMOの動きがしっかりとはまったのだと思います。
ー大変ありがたいお言葉です。まさに弊社のPMOチームの強みとして売っている「自ら必要なことを分析し、最大限に動く」というところをご評価頂けた結果なのかなとお話を聞いて思いました。引き続きガイオ様のプロジェクトを”グイグイ”支援させて頂きます!
現場が語るPMOとの協業
ーここからは、実際に現場でPMOと一緒に業務をされている皆様に、日々の働きぶりや印象的なエピソードについてお伺いしたいと思います。まず小林様、PMOには日々どのような業務を依頼されていますでしょうか。
小林様:日々の進捗管理をサポートして頂いたり、社内外を問わず会議の日程調整を一手に引き受けていただいています。また会議の議事録作成も積極的に対応頂き、非常に助かっています。そういった業務をPMOにお任せできるおかげで、私はプロジェクトの各メンバーとの対話に集中する時間が確保できています。これが大きなメリットだと感じています。

ーありがとうございます。安田様はいかがでしょうか。
安田様:私も主にプロジェクトのタスク管理や、数多くある会議の準備などを中心にお願いしています。PMOの方々にはプロジェクトマネージャー(PM)の仕事の一部を担っていただいている形です。PMの仕事には、技術的な調整からスケジュール管理、タスク管理、会議の調整まで多岐にわたる業務があります。
正直なところ、最初にPMOの方々と仕事を始めたときは、どこまで業務をお願いして良いのか分かりませんでした。個人的にはここまでお願いしたい、という範囲はあったのですが、果たしてそれがPMOの役割として適切なのか、少し懐疑的な気持ちもありました。そこで、お願いしたい業務をリストアップして岩井に相談したところ、「それがPMOを導入した目的なのだから、全く問題ない」と言ってもらえました。それ以来、PMの業務の中でも特にマネジメントに関わる部分を幅広くサポートしていただき、大変助かっています。技術的な判断や調整はPMが担うべきですが、それ以外のマネジメント業務を安心して任せられています。

オンライン環境下での工夫と岩井様への報告
ーPMOメンバーのAさんは、導入当初から支援を続けていらっしゃいますね。オンラインでの業務が基本となる中で、苦労した点や工夫してきた点について教えてください。
ウェッブアイ社員A:ガイオ・テクノロジー様でのPMO業務はオンラインが基本です。そのため、例えば小林様と初めて直接お会いしたのは、ご一緒してから3〜4ヶ月後の忘年会でしたし、安田様とも半年ほどお会いできないまま業務が始まりました。顔が見えない状態から、岩井様がおっしゃるように「グイグイ」と関係性を作っていかなければならない環境には、当初少し苦労しました。工夫した点としては、やはり人と人とのコミュニケーションを大切にすることです。会議前のほんの数分の雑談から始めたり、体調を崩してお休みされた方の翌日には「体調はもう大丈夫ですか?」と一言声をかけたりすることで、自ら接触機会を増やすように心がけました。こうした小さな積み重ねによって、少しずつ信頼関係を構築していったと感じています。

ー日々のプロジェクト支援に加えて、岩井様への複数プロジェクトの状況報告も重要な業務だと思いますが、その点についてはいかがでしょうか。
ウェッブアイ社員A:はい。担当している各プロジェクトが健全(ヘルシー)か否か、という点を、ほぼ毎営業日、岩井様に簡潔に報告する機会をいただいています。岩井様は全国を飛び回る非常にタイトなスケジュールで動かれているので、いかに短時間で分かりやすく報告するかが重要です。私たちは、まず「ヘルシーか否か」という結論から話し始め、その判断に至った経緯や理由を後から説明するように心がけています。この岩井様との報告を通じて、簡潔にコミュニケーションを取り、要点をまとめて報告するスキルが身についたと感じており、他の業務にも活かされています。
プロジェクトの「健全性」とPMO導入による変化
ーその「ヘルシーか否か」を判断する上で、岩井様がPMOに期待されているプロジェクトの判断基準はどのようなものでしょうか。
岩井様:プロジェクトの状態を、信号機の「青・黄・赤」で分かりやすく報告してほしいと伝えています。そして、黄色から赤に変わった時には、その理由と対策案も合わせて報告するように求めています。何をもってヘルシーとするかですが、一つ目は、お客様の要求に対して効果的な提案ができているか。二つ目は、宣言した計画通りに進捗しているか。そして三つ目は、人間関係です。お客様と我々、あるいは我々のチーム内での関係性といった、人が関わる要素がうまくいっているか。この三つ目の要素は、必ずしもデータとして表れるものではありません。オンライン環境の中で、そうした機微をどうやって汲み取るかが重要になります。
例えばPMOのメンバーは、「いつもはすぐに返信をくれるAさんの反応が、今日は0.5秒遅い。何かあったのかもしれない」といった些細な変化に気づきます。そうした違和感が数日続けば、プロジェクトの誰かに確認して裏付けを取る、といった動きをしてくれます。こうした人に関わるコンディションの把握も含めて、総合的にプロジェクトがヘルシーに進んでいるかを判断してもらっています。まだ道半ばではありますが、そのような視点を持つようにPMOのメンバーには伝えてきました。

ーウェッブアイのPMOが参画した後、社内にどのような具体的な変化や改善がありましたか。
岩井様:PMOを導入する前は、各プロジェクトがどうなっているのか、報告がなかったり、あっても要領を得なかったりで、状況把握が困難でした。関係者に電話で問い質すことが日常茶飯事でしたね。今ではプロジェクト数が120ほどに増えましたが、それらの状況を概ねカバーできているのは、間違いなくPMOの皆さんのおかげです。
また安田も話していましたが、世間一般で定義されるPMOは、プロジェクトに「伴走」して数値を計測するスタッフ、という位置づけかもしれません。しかし私は、そういうPMOは求めていません。我々が期待するのは、より踏み込んだ役割です。一時期、PMOのメンバーが我々の代わりに顧客とのミーティングでファシリテーションを行ってくれたことがありましたが、そうした動きができるようになって、私の期待するPMO像にかなり近づいてきたと感じています。
現場で実感するPMOの価値と「攻めのPMO」像
ー小林様は、現場レベルでPMOの支援が入ってから、どのような変化を感じましたか。
小林様:先ほどの「グイグイ来る」という話に戻りますが、例えばプロジェクトの状況が少し停滞している時に、「お客様と会議を設定した方が良いのでは?設定しますよ」と積極的に動いてくれます。自分でも気づいてはいたけれど、見て見ぬふりをしてしまっていた、あるいは手が回っていなかった部分を後押ししてもらえるので、非常に助かります。
また、報告スタイルの変化も大きかったです。以前は週に一度、お客様に進捗報告をしていましたが、PMOの方から「社内外に対して、毎日メールで進捗報告をしませんか?他のプロジェクトではそうしていますよ」と提案がありました。ウェッブアイのPMOは社内で情報共有をされているので、他のプロジェクトの良い事例をすぐに取り入れることができ、その日のうちに報告スタイルを変えることができました。これにより、プロジェクトの進め方のばらつきが減り、一定の品質レベルが保たれるようになったと感じています。

ー岩井様が期待されているPMO像について、もう少し詳しくお聞かせいただけますか。
岩井様:私が理想とするのは、単なる管理に留まらない「攻めのPMO」です。例えば、他社で協業しているPMOの中には、起業経験を活かして、我々の主要メンバーに代わって提案書を作成したり、お客様と積極的に対話し「ここにビジネスの種がありますよ」と我々のビジネス担当者に報告してきたりする方がいます。これはすごいことだと感じています。
このような動きができるようになれば、私が常々話しているPMOの完成形に近づいていくでしょう。もちろん人には一長一短ありますが、それぞれの強みを活かし、総合力として機能すれば、非常に価値のある活動になるはずです。
ーウェッブアイのPMOとして、その期待に応えていきたいですね。
ウェッブアイ社員B:はい。他社のPMOの方々とも関わる機会が増え、やり方は違うと言えど、見習うべき点が多くあることを実感しています。同じ環境で働くPMOとして、岩井様が求めるゴールに近いメンバーを目標に、そしていつかは追い越せるように、探りを入れて成長していきたいです。また、現在はプロジェクト管理だけでなく、安田様と一緒にビジネスの拡大・開拓という役割でもPMOとして参画させていただいています。営業活動や提案といった軸で進捗・課題管理を行う中で、ビジネスの種を見つけるという絶好の機会をいただいていると感じています。皆様と連携しながら、このチャンスを活かしていきたいです。

PMOに求められる資質と今後の展望
ー安田様は、PMOとの関わりの中で印象に残っているエピソードはありますか。
安田様:以前、定例会議が終わった後の雑談で、ウェッブアイのPMOの役割はテレビの「アナウンサー」に似ているな、という話をしたことがあります。一般的なPMOは指示待ちになりがちですが、我々が求めているのはそうではありません。ウェッブアイの皆さんのように、その場の状況に応じて機転を利かせ、場を仕切ることができる。アナウンサーがただ原稿を読むだけでなく、ゲストとの会話を盛り上げ、番組を進行させていくように、状況に応じた対応ができる点が重要だと感じています。特に難しいプロジェクトでは、コミュニケーション能力で突破口を開いてくれることを期待しています。

ーありがとうございます。PMOの役割を非常に分かりやすく表現していただきました。最後に、岩井様から今後のウェッブアイのPMOに期待することをお聞かせください。
岩井様:先ほどお話しした、私が考えるPMOのあるべき姿に近づけるよう、日々研鑽を積んでいただきたいです。もちろん、我々も皆さんにお願いするだけでなく、皆さんが成長できるような機会やきっかけを提供し、お互いにとってWin-Winの関係を築いていくことが理想だと考えています。以前、「3年で理想の形に」という話をしましたが、現在1年半が経ちました。残りの期間でその水準に到達できれば、御の字です。
ーこれからPMOの導入を検討している企業に向けて、ウェッブアイのPMOをお勧めするポイントがあれば教えていただけますでしょうか。
岩井様:もし、世間一般で言われるようなプロジェクトの進捗管理・計測を中心としたPMOではなく、もう一ランク上のビジネスをより強固に、より健全に発展させていくためのパートナーとしてのPMOを期待しているのであれば、ウェッブアイさんは検討の価値があると思います。彼らは、その高みに向かって努力を重ね、着実に成長しているメンバーを擁していますから。

ーご期待に応えられるよう今後もウェッブアイ社員一同、研鑽を積んで参ります!本日は、貴重なお話をいただき、誠にありがとうございました。
プロジェクトマネージャ支援サービス(支援型PMO)
プロジェクトマネジメントにかかわる基本を忠実に実行するには、知識と経験を併せ持った要員が必要です。プロジェクトマネージャ支援サービス(支援型PMO)では、お客様のプロジェクトマネジメント業務を代行(あるいは支援)します。プロジェクト運営のエキスパートが総合的にマネジメントすることによって、プロジェクトを確実に成功へと導きます。